【実体験】早生まれでもメリットある?3月生まれでも大丈夫な理由
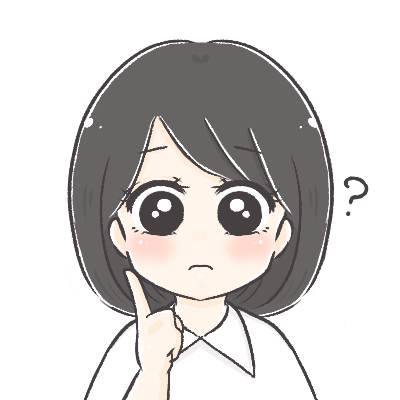
3月に産まれそうだけど早生まれで大丈夫かな

早生まれって周りと差がつきそうで不安

早生まれにはメリットもたくさんあります
出産をする際に、子どもが早生まれにならないか心配する人も多くいます。
中には妊活の時期から出産日を調整して、早生まれにならないようにしている家庭もいるほどです。
デメリットが多そうな早生まれですが、実はメリットも多く存在します。
この記事では、実際に3月生まれの赤ちゃんを育てている私が、育てている中で感じている早生まれのメリットを紹介します。
- 早生まれのメリット
- 早生まれのデメリット
- 早生まれと遅生まれの意味
物価高が進む中子どもの教育費を貯めるためには、まずお金のプロに相談して家計の見直しをすることが1番大事です。
私が家計を見直しするために相談したのは、リクルートが運営している保険チャンネルです。

保険チャンネル公式サイト:https://hokench.com/
オンラインで何度でも無料で相談することができる保険チャンネルは、保険だけではなくお金についてなんでも相談ができます。

教育費を貯めれるか不安がある人はFPに相談すれば、解決できるでしょう。

自宅にいながらオンライン相談ができます。
早生まれのメリットとは
早生まれの子どもを育てていて感じるメリットを紹介します。
- 社会性が身に付くのが早い
- 周りの子からの影響を受ける
- 生涯賃金が多くなる
早生まれは将来性に溢れていると思います。
それぞれの理由を紹介します。
社会性が身につくのが早い
早生まれの子どもは、集団生活の中で社会性が育ちやすい傾向があります。
特に保育園や幼稚園、小学校においては、同学年の中で年少の立場になるため、自然と周囲に合わせる力が身につきやすくなります。
早生まれの子どもは、4月生まれの子どもに比べて発達の面で遅れを感じることがあります。
そのため、集団生活の中で「自分がどう振る舞えばいいのか」を早くから考えるようになり、協調性や順応性が高まるとされています。
また、文部科学省の「幼児教育と保育に関する研究」によると、幼児期の環境適応能力は早期に養われた方が後の対人関係にも良い影響を与えることが分かっています。
特に「自分より成長の早い子どもたちと一緒に行動することで、模倣学習が活発に行われる」という研究結果もあり、これが社会性の成長につながると考えられます。
早生まれの子どもは、集団生活の中で自然と社会性を育む機会が多くなります。
自分より成長の早い子どもと一緒に過ごすことで、協調性や適応力が養われ、社会に出た際にも円滑な人間関係を築く力が身につきやすいと言えるでしょう。
周りの子からの影響が多い
早生まれの子どもは、同学年の中で年少の立場にいることが多いため、年上の子どもからの影響を受ける機会が多くなります。
このことが、知的好奇心の向上や新しいことへの適応力の高さにつながると言われています。
心理学的な観点から見ると、人間は「自分より少し上のレベルの環境」にいると、それを模倣することで成長する傾向があります。
これは「ゾーン・オブ・プロキシマル・ディベロップメント(最近接発達領域)」と呼ばれる考え方で、子どもが少し上の能力を持つ人と関わることで、発達が促されるという理論です。
また、実際に文部科学省の研究データでも、「異年齢の子どもと関わる機会が多い子どもは、社会性や語彙力が発達しやすい」という結果が出ています。
早生まれの子どもは、自然と学年内の年上の子どもと関わる機会が増えるため、この理論に当てはまりやすいと言えるでしょう。
生涯賃金が多くなる
早生まれの子どもは、一般的に「就職が早くなる」ため、生涯賃金が多くなる可能性があると言われています。
これは、働く期間が長くなるため、結果として生涯年収が増えることにつながるからです。
生涯賃金についての研究として、経済産業省や総務省のデータをもとにした統計があります。
それによると、日本の平均的な就労年数は、大学卒業後22歳から定年65歳までの43年間とされています。
早生まれの子どもは、同じ学年の遅生まれの子どもよりも最大で1年早く生まれているため、22歳時点での社会経験の差はほとんどないにもかかわらず、学歴や資格が同じならば早く就職できます。
そのため、遅生まれの子どもよりも1年分多く働ける計算になります。
例えば、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、日本の平均年収は約500万円とされています。
このデータをもとにすると、1年分の収入(約500万円)を多く得られる可能性があり、これが生涯賃金の差につながると考えられます。
早生まれの子どもは、結果的に同じ学年の遅生まれの子どもよりも1年長く働ける可能性があります。
これにより、生涯賃金が多くなり、将来的な経済的なメリットが生まれることがあるのです。
早生まれのデメリットとは
h3:0歳から保育園に入りずらい
日本では、保育園の入園は一般的に4月が基準となっています。そのため、早生まれ(1月~3月生まれ)の子どもは、生後すぐに0歳児クラスに申し込むことができず、途中入園のハードルが高くなります。
また、厚生労働省の「保育所等関連状況取りまとめ」によると、0歳児クラスの定員は1歳児クラスよりも少なく、特に途中入園の枠は非常に限られていることが分かっています。そのため、早生まれの子どもが4月の0歳児クラスに入れず、1歳児クラスでの入園を目指す場合、競争率がさらに高くなることがあります。
h3:周りの子と言葉や行動に差が出る
発達心理学の研究によると、幼児期の数か月の差は大きな違いを生みます。特に言語能力や運動能力の発達には個人差があり、4月生まれの子どもと3月生まれの子どもでは、ほぼ1年の成長差があります。
文部科学省の「幼児の発達調査」でも、同じ学年内での言葉の発達には差があり、遅生まれの子どもが早生まれの子どもに比べて語彙が多い傾向があることが分かっています。また、スポーツの分野でも、運動能力の発達の違いにより、早生まれの子どもが不利になりやすいというデータがあります。
h3:子ども手当が少ない
日本の「児童手当」は、0歳から中学卒業(15歳まで)を対象に支給されます。しかし、支給は「年度ごと(4月~翌年3月)」に行われるため、3月生まれの子どもは4月生まれの子どもに比べて、受け取れる期間が1年分短くなります。
具体的には、以下のような違いがあります。
| 生まれ月 | 受給開始 | 受給終了 | 受給年数 |
| 4月生まれ | 0歳4月 | 15歳3月 | 約15年間 |
| 3月生まれ | 0歳4月 | 15歳3月 | 約14年間 |
このように、早生まれの子どもは1年分の手当を受け取れないため、総額で約10万円~15万円程度の差が出ることになります。
早生まれと遅生まれとは
早生まれと遅生まれの違いは、主に「学年の区切り」によって決まります。日本の学校制度では、4月1日から翌年3月31日までに生まれた子どもが同じ学年に属するため、この区切りによって「早生まれ」と「遅生まれ」が生じます。
早生まれと遅生まれの定義
- 早生まれ:1月1日~3月31日生まれ
- 遅生まれ:4月1日~12月31日生まれ
特に、学年内での発達の差が影響しやすい幼少期においては、この区分が子どもの成長や学習能力に一定の違いをもたらすことがあります。
その理由や根拠
日本では、学年は「4月1日から翌年3月31日まで」に区切られています。しかし、国によっては学年の区切りが異なり、例えばアメリカやイギリスでは9月が学年の区切りとなるため、日本の早生まれに相当する子どもが、遅生まれとして扱われる場合があります。
この学年区切りの影響で、同じ学年の子どもたちの間で発達の差が生まれることがあります。特に、小学校入学時点では、4月生まれと3月生まれの子どもでは最大で1年近い成長の差があるため、体格や言葉の発達に差が生じることがあります。
また、スポーツの分野では、誕生月の影響が特に顕著に表れることがあり、例えば日本サッカー協会(JFA)のデータでは、ジュニア世代の代表選手の多くが4月~6月生まれであることが指摘されています。これは、幼少期の体力や運動能力の差が、選抜の段階で影響を及ぼすためと考えられます。
実例
- 「3月生まれの子どもは、小学校に入学した際に4月生まれの子と比べて体格が小さく、学習の進み具合にも差が出た。」
- 「早生まれの子どもは幼少期に学習面で苦労することがあるが、高学年になると成績の差は縮まる傾向がある。」
- 「スポーツの世界では、早生まれの子どもが不利になりやすいが、大人になると影響はなくなる。」
まとめ
早生まれと遅生まれは、日本の学年の区切りによって決まります。特に幼児期や学童期には発達の違いが影響しやすいですが、成長するにつれてその差は縮まる傾向があります。親としては、子どもの成長のペースを理解し、焦らずにサポートすることが大切です。
早生まれのメリットの口コミを紹介
早生まれのメリットで多い質問
1. 早生まれの子は発達が遅れるって本当ですか?
→ 回答
個人差はありますが、4月生まれの子と比べると体格や言葉の発達・運動能力などに差があることは自然なことです。しかし、成長とともにその差は小さくなります。その子のペースに合わせて関わり、無理なく発達をサポートすることが大切です。
2. 友達関係で不利になることはありますか?
→ 回答
年上の子たちが先に話せるようになったり、活動が得意になったりすることで、早生まれの子が「ついていけない」と感じることもあります。ただし、環境によっては周りが優しく助けてくれることが多く、年上の子たちとの関わりの中で社交性が育ちます。保育士としては、全員が楽しく遊べるように配慮しながら見守ります。
3. 運動面で遅れが出るのでは?
→ 回答
確かに、身長や体力の差が出やすいため、運動が苦手と感じることもあります。しかし、子どもは遊びや日々の活動を通じて自然に運動能力を伸ばしていきます。無理に競争させるのではなく、その子が「できた!」と感じる経験を増やすことが大切です。
4. 早生まれの子に合った接し方は?
→ 回答
「遅れている」と考えず、その子のペースを大切にします。言葉や動きがゆっくりな場合でも、しっかり目を合わせて話し、理解しやすい言葉を使うことで自信を持たせます。また、「〇〇ちゃんは〇〇が上手だね!」と、得意なことを見つけて褒めることが大切です。
5. 早生まれの子は自信をなくしやすい?
→ 回答
年齢が上の子と比べて「できない」と感じることが増えると、自信をなくすこともあります。そのため、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。「前より上手にできたね!」と成長を伝えることで、やる気を引き出せます。
6. 幼稚園・小学校に入るときに心配なことは?
→ 回答
園生活では成長に応じた保育を行っていますが、進学に不安を感じる保護者も多いです。特に、集団行動や学習面で遅れを心配することが多いですが、環境が変わることで急に成長する子もいます。無理に早くできるようにしようとせず、家庭でも「できることを増やす」より「楽しんで学ぶ」気持ちを育てることが大切です。
7. 早生まれの子のメリットは?
→ 回答
早生まれの子は、小さい頃から年上の子に囲まれて成長するため、観察力や適応力が育ちやすいです。また、努力する習慣がつきやすいので、長い目で見ると「負けず嫌い」「粘り強い」性格になりやすい傾向があります。

